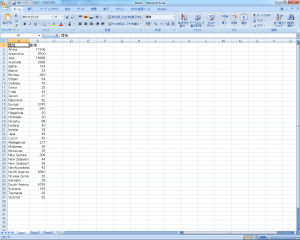12/5にLogicoolのゲーミングソフトウェアが更新されました。これは、同社のキーボードやマウスなど、ゲーム向けのドライバで、主な変更点は新しいゲームのプロファイルの追加ですが、バグフィックスも行われていることがあります。
現在、ゲームはあまりしませんが、メインのPCでG300マウスを使用しているので早速インストールしました。設定も引き継がれるので特に問題はなさそうです。Logicool Gaming Mouse G300はコストパフォーマンスも高く、使いやすいマウスです。ボタンの多さと設定の多様さはゲーミングマウスならではです。一方で有線式であること、ゲーミングマウスとしては普通ですが、一般的なマウスよりサイズが大きいこと、大きさの割に軽い作りであること、左右対称のデザインであることなどで好みが分かれるかもしれません。発売当初は3,400円ほどしていましたが、値段も手頃になってきました。
なお、ブラウザで表示されるOSの自動認識は正確ではないようです。ご注意を。