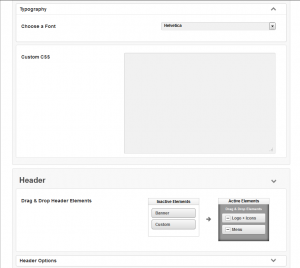他のサイトにも様々な意見がアップされていますが、Nikon D600を少しだけ触る機会がありましたので、感想です。
大きさ・重さは35mmフルサイズということを考える十分小さいかなという印象です。撮像素子でカメラの絶対的な大きさが決まる時代では無くなってきているのかもしれません。ファインダーは明るく見やすい印象です。接眼部の形状がD800の丸形では無く、好みの問題ではありますが、差別化されています。同じく、ファインダーの中に関連する項目ですが、AFポイントが中央付近に集中しています。中央1点でAFを固定して使う場合は良いのですが、もう少し幅広い面積をカバーしてもらいたいと思いました。
明るい普通の室内でのAFはスムーズに動きます。ただし、ライブビューの速度は相変わらずもっさりです。シャッタースピードは1/4000までになっています。
質感は悪くありませんが、D800と比べるとプラスチック感が少し強く、良くも悪くも中級機という印象です。ダイヤルなどもロックが付いていて気が利いています。
総合的な感想としては、価格が今後こなれてくれば、かなりお買い得感のあるモデルになりそうだという気がしました。ただし、撮影者に触れる部分(ファインダー接眼部、質感など)はD800とは違います。性能に関しても発売時期も近く、序列もはっきりとD800と区別されていますので、隣に置いて比べてしまうと、どうしてもD800に気が向いてしまいます。